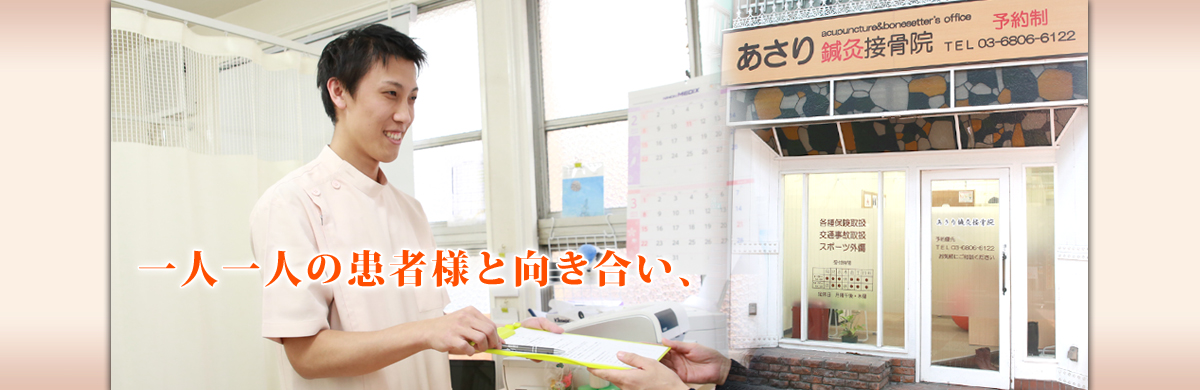




なかなか治らない。
スポーツ愛好家で整体、接骨院、整形外科、あちこち行っても治らない。
なぜなのか。
”治る”という言葉のイメージから
「身体の悪いところを良い状態に変化させる。」
そう思っている方がいらっしゃいますが
スポーツをしていてなかなか治らない方はそのパターンの治り方ではないことが多いです。
①筋肉が凝って硬くなっているからほぐす。
②関節が硬いから動かす。
③筋肉が弱いから筋力アップトレーニングをする。
③は言わずもがなで論外ですが今だにそう思っている方がいます。
では何が問題か。
動き方に問題があります。
運動には大きく分けて意識に伴った運動と無意識の運動の2種類がありますが両方大切です。
例をそれぞれにあげます。
一つ目の意識した運動
卓球をしていて肩が痛い。
肩周りの筋肉をほぐして、関節を動きやすくすれば一時的には寛解したように感じる。
しかし卓球の練習や試合で”背骨の動き”を伴わず手打ちになっていれば直ぐに戻ります。
また膝や臀部を落とさず打っていれば姿勢は猫背になり、
より肩甲骨は使えず肩の可動域は減り治らない方に進みます。
このケースは動きのパターンを変えていく必要があり
時間はかかりますが良くなります。
2つ目の無意識の運動の例は
長時間のスポーツで痛みが出るケースです。
腰、膝、肩でも当てはまります。
卓球、ゴルフ、野球、歩行。ランニングでもそうです。
これはかなり多いですが足をついた際に膝が内側に入ってしまうパターンです。
これにより膝の痛み、股関節制限、腰の反り腰、首のコリ、肘の痛みが治りにくくなります。
この運動パターンは足首のオーバープロネーションからの無意識運動なので
自力での改善は難しいです。
当院では運動療法とインストールを勧めています。
自動的に改善方向に導いてくれます。
治すということを本気で考えている方、気軽にお待ちしております。
南千住あさり鍼灸接骨院
アンチエイジングホルモンの代表は成長ホルモン。
成長ホルモンを分泌するのは、脳の下垂体です。
そのまま作用する場合もありますが、多くは成長ホルモンにより、肝臓や筋肉で作られIGF-1を介して働くきます。
成長ホルモンはその名の通り筋肉や骨などの成長を促し、子どもから大人へのカラダの成長と成熟を支えます。
成長が終わると分泌量は減っていきますが、大人も分泌しており、細胞の新陳代謝を促して全身にアンチェイジング作用を発揮します。
一日の成長ホルモンの分泌には波があり、もっとも分泌されやすいのは就寝して2〜3時間後に訪れる深い眠りの時間になります。
そして睡眠中に行われる心身のメンテナンスをサポートします。
眠りの質が下がり深い眠りが得られないと成長ホルモンの分泌量が落ち、エイジング(老化)は進みやすくなります。
成長ホルモンは、筋トレやランニングなどの運動時にも分泌されるので、適度な運動も不可欠です。
加えて大事なのは、一日のうちに空腹の時間をちゃんと設けること。
胃が空っぽになると、胃から食欲を促すグレリンというホルモンが分泌されます。
グレリンが成長ホルモンの分泌を促してくれるのです。
成長ホルモンは、血糖値を上げたり、体脂肪の分解を行います。
空腹時のエネルギー不足に備えるため、
グレリンが成長ホルモンの分泌を促進すると思われます。
空腹=若返りの時間とポジティブに捉え、間食、ダラダラ食い、夜食を避けましょう。
私も9月29日から食後の夜食を辞めました。
三ノ輪駅 南千住駅
南千住三ノ輪あさり鍼灸接骨院
別名「幸せホルモン」と呼ばれるオキシトシン。
妊婦が出産する際に脳から大量に分泌され、母性や幸福感をもたらすというのが、その所以です。
誰かとハグしたりスキンシップをすることでもオキシトシンは分泌され、
思いやりや絆を大切にする気持ちが育まれることが知られています。
そのオキシトシンが肌からも分泌されることが、近年明らかになりました。
肌に軽い刺激を与えると肌由来のオキシトシンが分泌され、表皮の再生を促します。
洗顔時はゴシゴシではなく優しくタッチすることでオキシトシンの美肌作用に期待できるという話もあります。
ポイントは優しくタッチするということ。
マッサージのような揉みほぐし、指圧ではこの働きが行いません。
特に首周りは神経が豊富で肌も敏感です。
マッサージで逆に悪化したという話は今だによく聞きます。
首肩が凝ると揉みたくなる気持ちはよくわかりますが結果的に悪化し、また硬くなります。
軽いタッチで行うことが重要です。
当院ではアスリートの筋肉アプローチ以外は
柔らかい施術か鍼治療を行っております。
その場しのぎであれば
激しいストレッチや痛みの強いマッサージ、痛み止めの薬が効果的かもしれません。
しかし南千住三ノ輪あさり鍼灸接骨院では
施術終わった直後の身体よりも
2週間後、3ヶ月後に身体が良くなっているかを考慮したアプローチを行っています。
なかなか治らない痛み、痺れがある方
定期的にギックリ腰になってしまう方、
気軽にご相談下さい。
三ノ輪駅 南千住駅、都電荒川線三ノ輪橋駅近く
南千住三ノ輪あさり鍼灸接骨院
今回はオキシトシンを掘り下げてブログにしたいと思います。
キシトシンは、出産と授乳に欠かせないホルモンとして知られていますが
出産も授乳もしない男性でも、オキシトシンは分泌されます。
オキシトシンには、家族や仲間との絆や信頼感を高める作用があるからです(男性でも、乳首への刺激でオキシトシンは分泌されるらしい)。
オキシトシンは、酸化を進めて老化のアクセルを踏むストレスと対抗する武器になります。
愛情ホルモン、幸せホルモンとも呼ばれるように、気持ちをハッピーにし、ストレスを和らげてくれます。
ストレス解消には、心の痛みや不安をシェアしてくれる仲間のサポートも心強いが、
オキシトシンはそうした絆を強化します。
ストレスがあると副腎からコルチゾールというホルモンが分泌され、
そしてコルチソールとオキシトシンには互いの分泌を抑える関係があり、
コルチゾールは、オキシトシンの分泌を抑え、オキシトシンは、コルチゾールの分泌を抑えます。
コルチゾールが出すぎると疲労も老化も進むのでオキシトシンでコルチゾールの過剰な分泌をセーブすることも有益になります。
この他にオキシトシンには、炎症を抑える抗炎症作用、筋肉や脅や神経を保護して再生させるといった多様な働きがあります。
最新の研究では、オキシトシンは肌の細胞からも分泌されており、表皮の再生を促すなど、肌のアンチエイジングにも一役買うと言われています。
オキシトシンは、ハグなどのスキンシップでも分泌が促されます。
しかしハグする相手がいなくても大丈夫です。
触り心地のいいベットや、ぬいぐるみを抱き締めるだけでも、オキシトシンは分泌されることがわかっています。
そしてオキシトシンに関して、最近ちょっと面白いことがわかってきたとのこと。
糖化で生じる悪玉物質のAGESが、オキシトシンに関しては、どうやらポジティブに働いているようです。
AGESは、糖質やタンパク質を含む食べ物を加熱すると生じます。
これはメイラード反応と呼ばれており、
こんがり焼けた食べ物の美味しさの元です。
人類が火を使うようになると、食べ物から入るAGESが増え、それにつれて受容体であるRAGEも増えたとのこと。
それによりオキシトシンが脳内に入りやすくなり、
その作用で脳が大きくなったり、
社会的な絆が強くなったりして、人類は文化や文明を発展させることができたという解釈も成り立つとのこと。
食後高血糖で生じる無駄なAGEsや高温加熱で焦げすぎのAGEsはNGですが
トーストや粉モンのようにこんがりキツネ色に焼けた料理のAGESは、適量ならオキシトシンを脳へ導くのにプラスになります。
そうした食べ物を仲間と美味しく味わう機会を増やせば、オキシトシンが増えて働きやすくなり、若返りも叶いそうです。
米井先生(同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター教授)参照
自律神経 南千住駅
南千住三ノ輪あさり鍼灸接骨院
目の前の食欲の言いなりになってしまうのは自分の意志が弱いから?
他人の言葉にすぐに凹んでしまうのは根性が足りないから?
これまでの人生でモテ期を経験したことがないのは口下手だから?
トレーニングをしても思ったほど
筋肉がつかないのは持って生まれた体質だから?
そうとも言えるしそうでないとも言える。
太る痩せる、
ストレスに強い弱い、
異性に対する共感力のありなし、
筋肥大しやすいしにくい、
これらすべてにはホルモンが関わっているからです。
性格や体質だから仕方ないと諦めていたことのほとんどは、ホルモンをコントロールすれば解決できる可能性があるということです。
「無理なく痩せたい」
「ストレスに強くなりたい」
「効率よく筋肉をつけたい」
「ついでに若く見られたい」、
それらの切実な願いはホルモンに可能性があります。
当院では全ての患者さまに
自律神経症状の改善プログラムを取り入れています。
その際にホルモンを介して行うことも分かっております。
ストレスから身を守るコルチゾール
幸せを感じるセロトニン
睡眠を促すメラトニン
愛情ホルモン、オキシトシン
などこれらは普段の施術で特に意識をしています。
身体は複雑系。
自律神経と内分泌系は異なるものですがお互い助けあって身体の中で活動しています。
どちらかが改善すればもう一方も改善方向に向かいます。
自律神経に不安のある方、気軽にご相談ください。
南千住駅、都電荒川線三ノ輪橋駅近く
南千住三ノ輪あさり鍼灸接骨院
今のご時世では
病気や怪我をスマホで調べれば
どんどん表示され、YouTubeやインスタグラム等のSNSでも
勝手に上がって嫌でも見られるようになっています。
しかし私はそれが正しい方向に進んでいるとは思いません。
症状がある逆にややこしくなっていることが多いからです。
腰が痛いで検索すると
原因は「臀部だ」、「足首だ」、「インナーマッスルだ」だとか
ストレッチや筋トレなど様々な方法が出てきます。
辛い症状があると情報にすがりたくなるので
一生懸命に色々なことをやります。
私も経験が豊富なのでよくわかります。
しかしこれが話をややこしくさせます。
完治というゴールを目指していたのに
実は全く違う方向に向かっていることがあるのです。
検索して手に入れた地図は違うゴールの地図だったということです。
人によっては「安静」が最短のゴールだったのにもかかわらず
ストレッチをして治らない状態が続くこともざらにあります。
当院では特に筋トレによってあらぬ方向に向かっている方が多いように思います。
それだけに情報には気を付けなければなりません。
こちらとしても最短ゴールを常に探っているのですがなかなか難しいものです。
特に3週間以上患っている方は専門家み診てもらうことを強くおすすめします。
三ノ輪駅 南千住駅 交通事故
南千住あさり鍼灸接骨院
本日も2つのホルモンを紹介します。
マイオカインというホルモンが認知機能の低下を防ぐことわかってきました。
運動することで筋肉は収縮・伸展を繰り返します。
すると筋肉からさまざまなホルモンが分泌されます。
こうした事実が分かってきたのが2000年代以降のことです。
これらのホルモンの総称をマイオカインといいます。
マイオカインのうちのIL-6やアイリシンというホルモンは
肥満や糖尿病の予防、SPARCは大腸がんの予防、IGF-1には認知症の予防効果が期待できるとのこと。
なかでも期待したいのは認知症予防効果です。
マイオカインを抽出した薬ができれば認知機能の維持に繋がります。
IGF-1以外のマイオカインが関与している可能性もあるので研究の進展が期待されています。
先ずは運動ですね。
2つ目のホルモンの紹介です。
脂肪燃焼、うつ改善のホルモン。
骨や筋肉を成長させる成長ホルモンは成長期にはなくてはならない大事なホルモンです。
しかしすでに成長しきった大人にとってもすごい効果が期待できるそうです。
微量の成長ホルモンが分泌されるだけで筋肉がつきやすくなり、
脂肪分解が促され、うつ傾向が解消されることが分かっています。
実際、中年になってお腹に脂肪が溜まって気分が晴れないという人に成長ホルモンを投与すると、
お腹が凹んで性格もポジティブになります。
ハリウッドセレブの中には成長ホルモンを投与している人もいるという噂もあります。
ただし月に30万円以上と費用は高額で、
がんのリスクを高めるというデメリットの報告もあるので何とも言えません。
やはり運動、、、
南千住あさり鍼灸接骨院
ホルモン最新研究を2つ紹介します。
1つ目はビタミンDです。
ビタミンDってホルモンではないですよね。
きのこや魚に含まれるビタミンD。
でもこれらの食品をロにせずともヒトはビタミンDを自前で作り出すことができます。
日光の紫外線を浴びるとコレステロールを材料にして皮膚内でビタミンDが作られます。
これが肝臓や腎臓に運ばれて活性型ビタミンDとなり、腸管からのカルシウム吸収を促してくれるのです。
役割としてはホルモンに近いですね。
となると、ビタミンDはただのビタミンではなくホルモン?
受容体に作用しないので厳密な意味ではホルモンとは言えません。
ただ、ビタミンDは骨の中の遺伝子レベルに働き、オステオカルシンというホルモンの分泌を促します。
このオステオカルシン、若返りホルモンとして注目を浴びています。
代謝調節、骨形成促進などの役割があると言われていますが
記憶・認知機能を改善、
インスリンの分泌を促進することで血糖値の上昇を抑制、
男性ホルモン(テストステロン)の分泌を促進し、生殖能力を高める、
他に運動能力を向上させたり、動脈硬化の予防、栄養素の吸収促進、脂肪の蓄積を抑える効果が分かっています。
この作用に関してはホルモンとして捉えてもいいかもしれない。
もう一つ紹介します。
女性ホルモン様物質というのをご存知でしょうか。
本物のホルモン専用の受容体にくっついて作用を発揮するのが「ホルモン様物質」と呼ばれるものです。
食品添加物や殺虫剤などに含まれるホルモン様物質は不妊症やがんなどのリスクを高めるといわれています。
これらを悪いホルモン様物質とすると、
カラダにいい働きをするホルモン様物質の代表格が大豆イソフラボンです。
こちらは女性ホルモンに似た作用をもたらします。
ただし、その作用が期待できるのは大豆イソフラボンの成分から腸内細菌が作り出すエクオールという物質。
日本人でエクオールを作る腸内細菌を持っているのは約50%。
若い世代ではこれが約20%に低下しているそうです。
もっと大豆を食べましょう。
納豆、豆乳がおすすめ。
個人的には国産がさらにおすすめかな。
三ノ輪駅近く
南千住あさり鍼灸接骨院
気温が激しく上下しても健康なヒトの体温は平熱に保たれている。
このようヒトには、外部の環境がどんに変わっても、内部の環境をなるべく一定に保っておく仕組みがあります。
これはホメオスタシス(恒常社)と呼ばれます。
ところが何らかの刺激を受け、そのホメオッッシスが崩れて内部環境が乱れることもあります。
それがストレスです。
ストレスとは、もともと物理学の用語。
力が物体に加わり、ひずみが生じた状態を指しています。
これをヒトに当てはめ、
ストレスと呼んだ生理学者ハンス・セリエは、
「ストレスは人生のスパイスだ」という名言を残しました。
確かに、人生にストレスは付き物ですし、
適度なストレスはやる気や活力を引き出してくれたりもします。
一方、ホメオスタシスを維持する回復力やその適応力(レジリエンス)を大きく超える強いストレスは、
スパイスどころか劇薬となり、心身に深ダメージを与えてしまいます。
このストレスからのレジリエンスでポイントとなるのが、ストレスを感じると分泌される各種ホルモンです。
ホルモンを分泌する内分泌系と、協力して働く自律神経系こそが、レジリエンスを担う主役となります。
平穏な日々を乱すストレスの種(ストレッサー)を少しでも減らす努力はしたいものですが
ハラスメントや新型コロナウイルス、急激なインフレのように、
自分の力だけでは対処が難しいものも少なくありません。
だからこそ、ホルモンを味方につけながら、
ストレスを良き人生のスパイスにしたいですね。
考え方、知識でそれは可能だと考えています。
自律神経専門
南千住三ノ輪あさり鍼灸接骨院